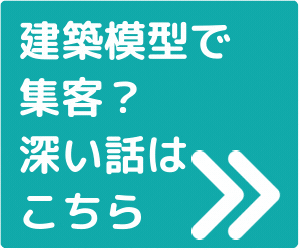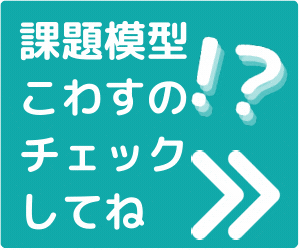テコです。
3Dプリンターの話題がメディアに出ることが少ない気がしています。もっと話題になっても良いのにね。(って、ハンドメイドの模型職人がなんてことを言っているんだ!)で、先日、劇団ひとりさんが3Dプリンターを購入して楽しんでいる記事を見つけて、思い切ってテコも購入することにしました。まだほんの2週間の使用ですが、模型職人としてメリット・デメリットをまとめています。対象商品は「業界最安値:LABISTS 3Dプリンター」です。業界最安値です!
業界最安値登場で初購入
3Dプリンターを知るようになってはや10年。活用したことはあっても購入までは敷居が高くて出来ずにいました。
その理由は、
- 高価
- 使い方が難しい
- 知識がない
- メンテナンスできない
- 用途が見当たらない
- サポートがない
- 国産が少ない
- トラブルが多い
と、まぁ、随分と出てくるものでした。
ところが、ここのところ3万円台の3Dプリンターが姿を現すようになってからというもの、購入者のレビューを拝読しては「やっぱメンテナンスが難だよなぁ・・・」「失敗談が多いよなぁ・・・」「知識ついていけないよなぁ・・・」と、なんとも気弱なことばかり思いながらも頭の中では9割方購入するつもりになっていました。
そして、ついに購入する日がやってきたのです。
「13,800円?!これなら失敗しても良い(わけないけど)んじゃない?」
と即座に購入ボタンを押したのでした。
5日ほど仕事で開封を我慢した後、晴れてYoutubeライブで開封の儀が執り行われました。
※Youtubeチャンネルは2021年3月に閉鎖しました
購入前の準備とは?
3Dプリンターを購入する前にやらなければいけないこと。それは紛れもなく”お勉強”です。基礎知識がなければ、そもそも何を買っていいのかも分かりません。
そもそも3Dプリンターって?
3Dプリンターとは、3次元データを立体物として出力する機器を言います。
コンビニや各家庭、職場にあるプリンターは2Dプリンターとも言い換えられますね。平面上に写真や文章を打ち出す機器なわけです。技術の進歩で、素材を熱で溶かして積層したり、光を当てて立体に固めたりすることができる3Dプリンターが誕生したんです。
7年ほど前は最安値5万円台というものもありましたが、ほとんどは知識不足で苦労する代物ばかり。まだまだ家庭用とは言い難い高価なものでした。
知識を蓄える
2020年は2~3万円台の3Dプリンターが随分と出てました。とはいえ、知識なしでは到底扱えないので事前に勉強は必要です。
どんな勉強が必要かというと、
- 3Dプリンターの種類(造形方式)
- 素材の種類
- 精度
- 機能
- 造形サイズ
- サポート体制(日本語対応)
それらの基礎知識を蓄えるために重宝するのがブログ記事とYoutube動画。
「3Dプリンター」と検索すれば最新の記事や動画がすぐに見つかります。意外にも、3Dプリンター経験者は多いんですね。
注意すべきは、常に”最新”の記事と動画をチェックすること。技術の進歩は目覚ましいものでいつも驚かされます。
ソフトの知識も必要
3Dプリンターは機器を買ってその知識を蓄えれば使えるというものではありません。3Dプリンターに流すデータを作る必要があります。あるいはインターネット上で見つけてくるにも知識が必要です。
3Dプリンターが立体物を印刷できるように、現時点では少なくとも2つのソフトを使いこなせる必要があるんです。それが、
- 3DCADソフト
- スライサーソフト
3DCAD(すりーでぃきゃど)とは、パソコンなどで図面を作図し自動化を促すテクノロジーで、3次元(立体)を認識します。このCADを用いて立体物を作ります。
スライサーソフトとは、初心者向きの造形方式「熱溶解積層方式」の3Dプリンターが認識できるように3次元データを変換するソフトです。どのくらいの温度で樹脂を溶かし何ミリの幅で積層するか、といった情報が組み込まれます。基本的には3Dプリンターに付属されるようです。
この2つのソフトが現時点では必要とされているようですから、3Dプリンターを使いたい方は覚える必要があります。
パソコンの種類も重要
テコは3Dプリンターを購入する前に、Chromebookも購入しています。10年物のWindows10(32ビット)とドン・キホーテの爆安ノートパソコンを持っていましたが、諸々の事情でChromebookをメインマシンにしようと試行錯誤しています。
購入したのはChromebookの中ではちょっとハイグレードなこちら。なんと、1か月半待ちの大人気機種です。
これら3台のノートパソコンとMacブックの情報を調べて分かったのですが、3Dプリンターを使うために必要なソフトは、パソコンの性能というより種類に左右されてしまいます。
まとめてみると、
- WindowsOS、MacOS、ChromeOSの中ではWindowsOSが有利
- WindowsOSの中でも、Windows10が断然安心
- 簡単な3Dなら非力なパソコンでもOK!
- 32ビットでは非対応のソフトも!64ビットパソコンにしよう
ということで、テコ所有の3つのパソコン、
- Windows10(32ビット)ハイスペックパソコン
- Windows10(64ビット)爆安ドンキパソコン
- Chromebookちょっとハイスペックパソコン
の中で、最も使えるパソコンは、
- Windows10(64ビット)爆安ドンキパソコン
という意外な結果になりました。
ちなみに、2020年9月に最新のバク安ドンキパソコンMUGA3が発売されています。ただし、あくまで遊び程度です。本格的にCGなども含め始めたい方はやはりハイスペックなものをお勧めします。
プチまとめ
ここまでをちょっとまとめると、
「3Dプリンターを買う前に基礎知識を学び、必要なソフトが動作するパソコンを用意する」
ということですね。
なので、せっかく買ったChromebookは今のところ3Dプリンターのために使うことはありません^^;
住宅模型作りに活用
さて、今回の記事では基礎知識的なことは割愛させて頂き、本題の住宅模型作りに3Dプリンターが向いているのか、そのメリットとデメリットをまとめます。
10年前最先端の実力
2012年頃、3Dプリンターを専門に扱う会社の社長と対談したことがありました。当時は最先端を行く精鋭企業で社員は数名。今でいうスタートアップ企業の先駆けみたいなものですね。元々、印刷業界にいた方でしたから、早い段階で業界に訪れる激震を予見し動いていたようです。ちなみに、今はDMMに買収され、3Dプリンターサービスの中枢に組み込まれた企業です。
当時の高性能3Dプリンターによる作品がこちらです。

当時、フルカラーといえば1千万円を超えるような超高額3Dプリンターだったと思われます。初めて知ったテコは、ちょっとビビりました^^;
2020年最安値の実力
最安値3Dプリンターで出力した造形物を写真で見てみましょう。
まずはサンプルデータのロケットやダウンロードさせて頂いたピカチュウなどの模型です。

どうです?
特に難しい設定をしなくてもとてもきれいなロケットが印刷されました。ピカチュウや富士山、フリーソフトで作った文字の印刷もなかなかなものです。
※参考 (My Mini Factory)
ピカチュウ:https://www.myminifactory.com/users/PatrickFanart
富士山:https://www.myminifactory.com/object/3d-print-mt-fuji-68670
最安値の3Dプリンターで出力したとは思えない仕上がりですが、では、サンプルではなく、自分で作ったデータならどう?と思い、2つ作ってみました。上の写真の右2つ(テキスト”teco”と黒い物体)がそうなんですが、黒い物体はこんなところに使われます。

そう、椅子の脚。
この脚の部品が4年前のお引越しの際に4脚のうちのたった1つ紛失してしまっていました。もちろん、ずっと物置にしまって使うことがなかったのですが、こうして無事、日の目を見る日を迎えました^^
といった具合に、フルカラーとはいきませんが、日用品として使えるグレードでしっかり印刷してくれます。
模型用の人型はうまくいく?
ということで、ちょっと期待しながら模型で使われる人型を出してみることにしました。
使ったデータは、昔からテコがCADで描いた2次元の人型に3DCADで厚みを与えたオリジナルです。
そのデータで印刷した写真がこちら。

あ~、やってしまいましたぁ・・・;;
もうガタガタです。S=1/100とS=1/50とS=1/75のサイズ、それぞれ約17mm、約34mm、約23mmの大きさです。厚みは1mm。
見ての通り、折れてしまうものもあれば、男女の区別もつかないものも。最もうまくいったS=1/50でもとても荒い仕上がりでした。写真の大きな男性はこれでもキレイに整えたほうです。同じサイズの女性は残念ながらキレイに整える途中で折れてしまいました。
印刷の仕方、例えば寝かせるとかしてあげればまた違うかもしれませんが、寝かせたら寝かせたで、足元の土台が安定しないでしょうし、別個で印刷して後で接着するなんて手間が掛かって・・・

最安値の3Dプリンターに高精度を求めても仕方ありませんが、手作りの紙製人型と並べても質の差は歴然。やっぱり手作りのほうがまだ良いなぁ。
メリットとデメリット
ここまで見てきて、住宅模型職人にとって3Dプリンターの導入にはどんなメリットがあるんでしょう?
デメリット
模型を作るうえで大切なのは、いかに正確に立体物として表現するかです。それが実在しない未知のものならまだしも、実際に建つ住宅となると間違いはできません。住む方々の検討材料として正確なものをお作りする必要があるからです。
模型職人の視点から考えると、以下のことも大切です。
- 納期に間に合うか
- 技術的に可能か
- 価格とのギャップがないか
これはすなわち、
「期待以上のものを効率良く適正価格で納品できるか」
ということですよね。
3Dプリンターは以下のことを加味する必要があります。
- 本体価格
- 精度
- 速度
- 作成サイズ
- 自己メンテナンス
- メーカーサポート
- 材料費
- 3Dデータ作成
- 仕上げ
実は手作り模型の手間とそれほど差はないことが今回の3Dプリンター購入で分かりました。手間をかけた割に材料費や仕上げに要する時間が意外に多いため、手作りより損をしてしまうことがあるかもしれないんです。

上の写真は、3Dプリンターが立体物を印刷した直後の状態です。サポート材がピカチュウの耳や尻尾を支えているのが分かります。これらをキレイに取り除き、積層のラインを磨いて滑らかにし、コーティングして塗装して・・・ということになるわけですね。
テコはそんな手間暇掛けるのが苦手なので、黒ピカチュウ&白ピカチュウのまま息子にプレゼントしてしまいました^^;

メリット
では、メリットはないのか?というと、大いにあると思います。
模型職人さんは、紙製(スチレンボード)模型、プラスチック模型、3Dプリント模型に分かれますが、それぞれを今後して使うことはまだそれほど多くはありません。
メリットとしては、
- 部分的に3Dプリント化する
- 模型作りに必要な治具(ジグ)を作る
- 日常に生かす
の3つが考えられ、特に部分的に3Dプリントして活用する点では、これからの模型職人さんにメリットがあると思われます。
例えばこんなものが既製品で販売されています。
- 人型
- 車
- 便器
- キッチン台
- 洗面台
- 浴槽
- 樹木
でも、これらはちょっと割高なんです。欠品に備えて買いだめしても古くなれば色あせや黄ばみで使えなくなります。
3Dプリンターが使える環境なら、必要な数だけ必要な時に印刷できます。
残念ながら、テコが購入した最安値3Dプリンターでは人の形は微妙でしたが、3~5万円台の中にはかなり優秀なものもあるので、車とか便器とかはかなり使えるのではないかと思います。
まとめ
約2週間、最安値3Dプリンターを使ってきて分かったメリットとデメリット。
一般的なことをまとめますと、
- メリット
- 手軽に始められる価格になった
- フリーデータが手軽に手に入るようになった
- 日常品の部品を自分で作れるようになった
- デメリット
- スタート前の知識が必要
- メンテナンスが大変
- 手づくりと同様に手間が掛かる
住宅模型活用の点からまとめますと、
- メリット
- 小物部品を低価格でストックできる
- データさえあれば何度も印刷できる
- デメリット
- データ作成が大変
- 住宅一棟分の印刷は大きな設備投資が必要
- サポート(維持)費が掛かる
総じて、
小物に3Dプリンターを活用し、手作りと上手く住み分けする
ことで住宅模型づくりも楽しくできるのではないでしょうか。
なんだかんだ言って、椅子の脚を作成することができて、それが最も大きな収穫だったんですけどね ^。^